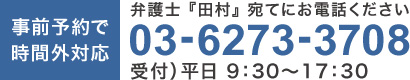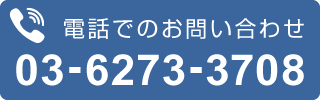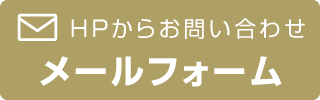Posts Tagged ‘交通事故’
交通事故で賠償金の分割払いはできる?弁護士が解説

このコラムのまとめ
- 交通事故の賠償金は一括払いが基本。
- 後遺障害逸失利益の事案で、被害者が求めた場合、場合によっては定期金賠償が認められる。
- 加害者が分割払いを求めることは原則としてできないが、場合によっては認められる。
- 分割払い中に被害者が死亡しても、決められた分は支払わなければならない。
賠償金はどうやって払う?
交通事故で相手にケガをさせたり、車を壊したりした場合に、あなやは賠償金を払うことになるでしょう。
その時、普通は無制限の任意保険に入っているでしょうから、決まった賠償金が高くて払えないということはあまりないでしょう。
そして、交通事故の賠償金は、普通、一括で支払わなければなりません。
仮に何千万円もの賠償を命じられたら、一括で払うのことは困難でしょう。そのためにも自動車保険(任意保険)は必ず加入した方がいいですね。
分割払いできるか?
この賠償金を分割払いすることはできるでしょうか。
被害者とその内容で示談できれば可能ですが、判決で一括払いを命じられたら、これを分割で払うことはできません。
では、被害者(原告)は判決で分割払いを求めることは可能でしょうか。
ここで、被害者が重い後遺障害を負った事件で、後遺障害による逸失利益について分割払い判決(定期金賠償といいます)ができるかが争われた事案が参考になります(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)。
定期金賠償制度は、変更判決制度(民訴法117条)と相まって、長い期間に渡って被害が続いて、状況が変化する可能性がある事件では、状態が悪化するにせよよくなるにせよ、それに対応して賠償額を変更できる可能性があります。
重い後遺障害によって働けなくなったことの賠償である逸失利益の場合は、特に被害者が若い場合にはよりよくなる可能性だってあるので、定期金賠償を認めることは公平であると考えられます。
この判例は、
- 原告が定期金賠償を求める旨の申し立てをしていること
- 不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められること
の二つの条件を満たせば、後遺障害逸失利益の分割払い判決(定期金賠償)は可能であると判断しました。
この裁判では、被害者が事故当時まだ4歳であった(つまりこの後長く生きる可能性がある)こと、高次脳機能障害という重い後遺症であったことから、二つ目の要件である「相当性」が認められるとして分割払い判決(定期金賠償)を認めました。
加害者(被告)が分割払いを要求できるのか
ところで、加害者の方が分割払いを求めることはできるのでしょうか。
東京高判平成15・7・29 は、将来の介護費用につき、原告が一時金賠償を求めたにもかかわらず、被告の主張した定期金賠償を採用しました。
場合によっては、裁判所が認めてくれることもあるでしょう。
分割払いをしてるうちに被害者がお亡くなりになったら、逸失利益はもう払わなくて良いの?
後遺障害による逸失利益は、就労可能期間(67歳まで)に得られたであろう収入を労働能力を喪失した割合を考慮して決められます。
そして、定期金賠償というのは、原則的に被害者が死亡したときに打ち切られるのが原則の制度です。
では、分割払いをしている途中で被害者が死亡した場合は、そこで逸失利益の支払は終わるのでしょうか。
例えば介護費用などは、死亡時点で支払は終わると考えられています。
この判例(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)では後遺障害による逸失利益の支払が終了するかが争われました。
最高裁は、特段の事情が無い限り、就労可能期間の終期よりも前に死亡しても、支払は継続しなければならないと判断しました。
最高裁判所は、定期金賠償制度の性質論よりも、交通事故による重傷者と死亡者とのバランスを重視しました。
残された問題
分割払い判決ができるかは、未だ全部の場合に可能と判断されてはいません。
この判例では後遺障害逸失利益の賠償を分割支払にできるかが争われましたが、例えば、被害者が死亡した場合の逸失利益に対して定期金賠償ができるのかは、未だ最高裁判所は判断していません。
例えば、一家の大黒柱が死亡した場合には、状況によって、一括払いしてもらわないと困る事案があるかと思います(子の進学費用が重なったりと、大きな出費が一度に生じることなど)。
そもそも、死亡した場合には将来の状況の変化がありえないため、定期金賠償にするメリットがありません。
私見としては、死亡逸失利益の場合は一括払いがふさわしいと考えます。
交通事故の逸失利益、減収がなくてももらえるの?弁護士が解説

この記事のまとめ
交通事故で身体にダメージを負っても、実際に収入が減らなければ逸失利益がもらえないのが原則です。
ですが、自分の特別な努力で減収を防いだなら、それを具体的にアピールすることで裁判所が逸失利益を認めることがあります。
がんばって働いたら収入が減らなかった!
交通事故で身体に被害を受けると、おもうように働けなくなることがあります。
その結果、収入が減ることもあります。
このような事故が無ければ得られた利益を「逸失利益」といいます。
当然逸失利益も交通事故の損害なので、加害者に請求したいところです。
ところが、身体がつらくても頑張って働いた人の中には、収入が減らなかった人もいるでしょう。
この場合にも、逸失利益はあるのでしょうか。
裁判所は差額を払うべきと考えている
後遺症によって収入が減る逸失利益については、二つの考え方があります。
ひとつは、働く能力自体が損なわれたのであるから、喪われた労働能力自体が損害であるという考え方です(労働能力喪失説)。
自賠責保険の後遺障害等級はこの考え方を基にしています。
後遺障害等級は、実際に減収が発生している場合には、裁判所はこれをベースに損害を認定します。
しかし、裁判所は基本的には、あるべき収入と現実収入との差額を損害とみています(差額説)。
ですので、等級認定があったとしても、実際に収入減少しなかった場合には逸失利益を認めないのが原則となっています(最判昭和42年11月10日民集21巻9号2352頁)。
一方、仮に収入が減らなくても、特別の努力をしたことによって収入が減らなかった場合や、昇級や転職に不利益が生じるおそれがある場合などの特段の事情がある場合には逸失利益を認めるとの判断をしました(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁)。
どんな場合に逸失利益が認められるの?
では、上記の「特段の事情」とはどのような場合でしょうか。
今までの裁判例では主に以下のような場合に特段の事情が認められました。
(東麗子「減収が無い場合の逸失利益算定の認定傾向について」交通事故相談ニュース47号2頁参照)
・昇進や昇給に不利益が生じるおそれ
・具体的な業務への支障
・転職
・本人の努力(具体的に)
・周囲の助力
このほかにも事案に応じた要素が検討されますので、これに限らないでしょう。
どのくらいの額が認められるの?
特段の事情が認められれば、後遺障害認定どおりの逸失利益が認められる場合もあれば、それより減額して認める裁判例も多いようです。
頑張りをみとめてもらおう
このように、実際には収入が減少していなくても、その努力を裁判所が認めてくれる場合があるのです。
交通事故の逸失利益がとれないとあきらめないで、自分や周囲の努力、将来への不安などをアピールしましょう。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
物損と人損の複雑な関係!同じ事故でも消滅時効の期間がちがう?弁護士が解説

このコラムのまとめ
交通事故において、人損と物損は消滅時効の起算点や期間が異なります。
最高裁は、物損については、症状固定時からではなく、多くの場合は事故発生時から消滅時効期間が進行すると判断しました。
物損については、人損よりも先に和解や提訴をしなければならない場合があるでしょう。
消滅時効は常に意識しなければならない
交通事故を法律問題として扱うとき、そこにはたくさんの論点があります。
その中でも、実際に大きな影響を及ぼすものに、消滅時効があります。仮に消滅時効期間を過ぎてしまった後では、加害者に時効を援用されたら、被害者は損害賠償請求できません。
ミスした場合の損失が大きいため、消滅時効を意識することはとても重要です。
ところで、交通事故には、身体や生命の損害である「人損」と、車など物の損害である「物損」があります。
消滅時効は、この損害の種類によって異なるのでしょうか。
人損の消滅時効期間
身体の傷害(人損)の消滅時効の開始時期は加害者と損害を知ったときから5年です。条文は以下のようになっています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
改正後の民法によると、724条の2が適用されるわけですね。
人損の時効の起算点
人損の消滅時効は,いつから開始するのでしょうか。
死亡の場合を除いて、人損は要するにケガです。ケガはおおくの場合だんだんと治癒していきます。
治療の結果、もうこれ以上治らない、という時点(「症状固定時」といいます)から時効は進行します(後遺障害による損害の場合です。厳密には治療費は事故発生時から消滅時効期間が進行すると考えられますが、実務上、症状固定時からと扱うことがあります)。
交通事故でケガをしたら、入院や通院などして普通はしばらく治療します。ですので、事故後すぐに症状固定とは通常なりません。
物損の消滅時効期間や起算点
交通事故では、人損がある場合,普通は物損も生じることが多いですね。物損の消滅時効はどうなっているのでしょうか。
まず、物損の場合は、民724条が適用されますから、消滅時効期間は3年です。
次に、物損はいつから時効期間がスタートするのでしょうか。消滅時効の起算点の問題です。
物損は、要するに車両等の破壊ですが、普通は、交通事故が発生した時点で、当事者は車などが破壊されたことを認識します。
ですので、物損の消滅時効の起算点は、ほとんどの場合、事故発生時となるでしょう。
先に物損が消滅時効にかかってしまう?
ところで、物損は事故発生後すぐに時効期間が開始して3年で時効になりますが、人損はケガの症状固定まで時効が開始しませんし、開始しても5年です。
そうすると、交通事故で物損と人損の両方があった場合、物損が先に消滅時効にかかるのでしょうか。
最高裁は物損の消滅時効は事故の時から進行すると判断
この点,先に物損が時効にかかるとすると,症状固定まで長く掛かっている事案の場合は物損については先に提訴せざるを得ません。
これでは過失割合など、人損と重複する論点を先行して争う必要が生じて面倒です。
しかし,最高裁は,人損と物損は別であるとして,基本的に物損の加害者と被害を知ったとき(ほとんどの場合は事故時でしょう)から時効は進行するとしました(最高裁判所第三小法廷令和2年(受)第1252号 令和3年11月2日判決)。
このため,人損も物損もまとめて症状固定後に争うと言うわけにはいきません。先に物損を提訴しないと物損が消滅時効にかかってしまいます。
ただし,過失割合に争いがない場合には,先行して物損が解決することも多いでしょう。場合によっては、加害者と消滅時効を主張しないとの合意が取れる可能性もあります。
物損の時効にも目配りを
今後は,物損の消滅時効期間についても気をつけて,時効完成前に提訴する必要があります。
人損も物損もあって過失割合に争いがあり,かつ症状固定まで時間が掛かる場合には注意が必要です。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
盗まれた自動車が事故!それって持ち主に責任あるの?弁護士が解説

この記事のまとめ
盗まれた自動車が事故を起こした場合でも、キーを刺しっぱなし、施錠しないなど管理に問題があれば所有者も責任を問われます。
きちんと自動車を管理するとともに、任意保険など万一の補償を掛けましょう。
泥棒が悪いはず!
ある日、自分の大切な自動車が盗まれたらショックですよね。
もう帰ってこないと諦めかけたとき、警察から電話が!やったと思ったら、誰かが勝手に運転して事故ったとのこと。
盗まれて壊された上に、事故の被害者から損害賠償請求をされたら、もう踏んだり蹴ったりですよね。
そんなの泥棒が悪いはず!そのお気持ちはよくわかります。
盗まれた所有者が責任を負わされる?
こんな場合、所有者は事故の被害者に損害賠償しなければいけないのでしょうか。
結論から言うと、責任を負う場合があります。
まず人身事故の事案で、最高裁は所有者の責任を認めました(最判昭和48年12月20日民集27巻11号1611頁)。
この事案では、ドアに鍵をかけず、エンジンキーをさしたまま、外から入りやすい車庫に入れていた事案でした(なお、民法709条でなく自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)の事案)。
たしかに、この事案では、盗もうと思えば誰でも簡単に盗める状態で、大変不用心でした。自動車はひとたび暴れ出すと危険な凶器にもなります。ですので、きちんと管理することが求められているのです。
仮に、起爆スイッチ付の爆弾を自宅前にポンと置いといたら、そりゃ管理責任を問われますよね。自動車のその延長線上にあると考えてはどうでしょうか。
ポイントはきちんと管理していたかどうか
一方で、自由に入れない場所にキーを保管し、ドアを施錠していた(少なくともそう決めていた)などの場合には、最高裁は所有者の責任を認めませんでした(最判令和2年1月21日交民53巻1号1頁)。
やはり、車を施錠するなどきちんと保管していることがポイントになっています。
任意保険に入っていれば保険金が出る
仮に盗まれた所有者に責任が認められても、自賠責保険や任意保険を使うことができます。
まずはきちんと車両を管理する、そしてきちんとした補償内容の任意保険に加入することが、一番大切ですね。
それと、弁護士特約も忘れないで!
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。